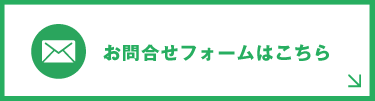オフィシャルブログ
バイオプラスチックのやさしい解説
バイオマスプラスチック
バイオマスプラスチックは、サトウキビやトウモロコシ、ジャガイモのデンプンなど「育て直せる植物」を原料にしたプラスチックです。植物は成長のあいだに二酸化炭素(CO₂)を吸収します。だから、この材料を使うと、石油だけに頼るよりもCO₂の増加をおさえやすく、脱炭素に役立つと期待されています。限りある化石資源の使用量を減らせるのも強みです。ただし「植物から作った=自然に土に戻る」とは限りません。分解するかどうかは材料ごとに異なります。
バイオプラスチック(広い言い方)
よく似た言葉に「バイオプラスチック」があります。これは生物に関係するプラスチックの総称で、二つのグループを合わせた広い呼び方です。①原料が植物などの再生可能資源であるバイオ由来(バイオベース)のもの。ここにバイオマスプラスチックが含まれます。②特定の環境で微生物の働きにより分かれていく生分解性のもの。中には、植物由来でないのに生分解する樹脂もあります。つまり、バイオプラスチックは「バイオ由来」か「生分解性」のどちらか、または両方を満たす広いグループなのです。
生分解性プラスチック
生分解性プラスチックは、温度や湿度、微生物など条件がそろうと小さな分子まで分かれていく性質を持ちます。家庭の庭土のような低い温度では進みにくい場合もあり、いつでもどこでも自然に消えるわけではありません。利点を活かすには、適した環境で処理する流れが必要だと覚えておきましょう。生分解性かどうかは「どんな原料で作ったか」とは別の軸の話です。
どこで使われている?
バイオマスプラスチックは、レジ袋、食品容器、ストロー、文房具など身近な場所で使われています。さらに、家電の部品や自動車の内装材といった産業分野にも広がっています。見た目や使い心地は従来のプラスチックに近いように工夫され、気づかないうちに置き換わっていることもあります。
よい点と注意点
良い点は、化石資源への依存を減らせることと、CO₂の面で有利になりやすいことです。一方で、作るコストが高くなりがちなこと、天候や収穫量に左右されて原料の確保がむずかしいことが課題です。生分解性タイプは、性能を発揮できる条件が限られるため、混同せずに理解することが大切です。製品を見るときは「どれだけ植物由来か(バイオ由来率)」と「生分解性の有無」をそれぞれ確認すると、特長がつかみやすくなります。
まとめ:三つの関係
・バイオマスプラスチック=植物を原料にしたプラスチック(生分解するとは限らない)
・バイオプラスチック=「バイオ由来」または「生分解性」、もしくは両方を含む広い仲間
・生分解性プラスチック=適した環境で分かれていく性質をもつプラスチック
この違いを理解し、使う場面や処理方法まで考えて選ぶことが、便利さを保ちながら環境への負担を減らすコツです。